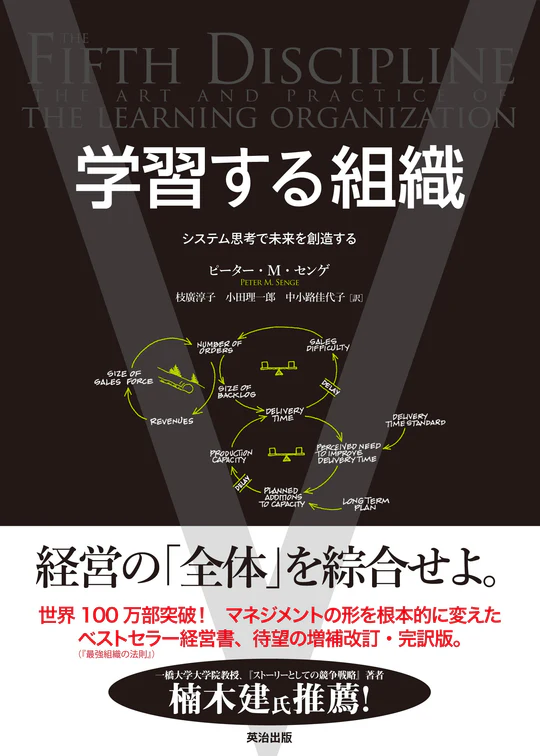イントレプレナー塾
「学習する組織」とは?小規模組織でも成長し続ける仕組みと5つの実践方法
著:インキュベーションコンサルタント 菅野 悠
小規模な教育機関で組織運営を担っていた頃、悩まされていたのは「情報共有の不足」や「同じミスの繰り返し」でした。どうすれば小さな組織でも自律的に成長できるのか――職員15名ほどの専門学校で模索する中で出会ったのが、「学習する組織」という考え方です。
本稿は、ウェディング・ホテル専門学校の新規設置から運営までを担い、広報責任者・運営責任者として約10年にわたり教育現場に携わってきた、弊社インキュベーションコンサルタントの菅野が、その実践経験をもとにまとめたものです。
コンサルタントとしてさまざまな現場を支援する中でも、この考え方は企業規模を問わず有効であり、再現性があると確信しています。ぜひ、組織づくりに悩む皆様の参考になれば幸いです。

私が前職で運営していた専門学校は、職員15名程度、学科2つ、部署も4つという比較的小規模な組織でした。しかし、その規模だからこそ、情報共有やスタッフ間の思考の構造化が非常に重要でした。そして、この小さな組織をうまく機能させるために、「学習する組織(Learning Organization)」の概念を強く意識し、実践してきました。
学習する組織とは、単に個人が学ぶだけでなく、組織全体が継続的に学び、適応し、進化する仕組みを持つ組織のことを指します。今回は、私の経験をもとに、学習する組織の特徴と、それを現場でどのように活かしたのかを解説します。
目次
1. なぜ「学習する組織」が必要なのか?
組織が学習しなければ、同じ問題が何度も繰り返されます。特に、小規模な組織では、一つの問題が全体に影響を及ぼしやすく、早期の対応が求められます。私の経験では、以下のような問題が頻繁に発生していました。

・情報共有の不足:部署や担当者ごとに知識が分散し、適切な人に情報が届かない。
・問題の再発:同じミスが繰り返されるが、根本原因が共有・分析されないため改善が進まない。
・構造的な問題の見落とし:個々の業務の中では問題が見えにくく、組織全体としての課題が把握しにくい。
こうした課題を解決するために、組織が学び続ける仕組みを作ることが不可欠でした。
2. 学習する組織の5つのディシプリン
「学習する組織(Learning Organization)」とは、目的に向けて効果的に行動するために、集団としての“意識”と“能力”を継続的に高め、伸ばし続ける組織であると定義されています。
出典:ピーター・M・センゲ(著)/枝廣淳子(訳)『学習する組織 ― システム思考で未来を創造する』英治出版
この考え方は、単なる理念ではなく、具体的な理論と実践手法に裏打ちされています。中でも中核となるのが、「学習する組織の5つのディシプリン(規律)」です。
ここでは、ピーター・センゲが提唱するこの5つのディシプリンに沿って、私たちが現場でどのように実践してきたかをご紹介します。
(1) システム思考(Systems Thinking)
問題は単独ではなく、全体の流れの中で発生する。 例えば、学生募集の問題が生じたとき、単に「広告が足りない」や「担当者のスキル不足」と結論づけるのではなく、募集から入学、授業運営、卒業までの流れの中で何がボトルネックになっているのかを分析しました。
実践例:
・学生の進学動機を分析し、カリキュラムとPR戦略を再設計。
・広報担当だけでなく、教員や事務スタッフとも情報を共有し、一貫性のあるコミュニケーションを確立。
(2) 自己マスタリー(Personal Mastery)
個人の成長なくして組織の成長なし。 職員が自身の仕事の目的を理解し、スキルを高め続けることが、組織全体の力になります。
実践例:
・各職員が「自分の業務の目的」を明確にし、それを定期的に見直す場を設定。
・研修だけでなく、日々の業務の中で学べる環境を整備(例えば、日報に「今日学んだこと」を記載)。
(3) メンタルモデル(Mental Models)
人は無意識のうちに特定の思考パターンに縛られている。 例えば、「この方法でずっとやってきたから変えられない」「新しいアイデアはリスクがある」といった固定観念が、組織の進化を妨げます。
実践例:
・定期的な振り返りミーティングを設け、「なぜこのやり方を続けているのか?」と問い直す文化を作る。
・新しい方法を試すための小さな実験を推奨し、「失敗しても学びを得ることが目的」とするマインドセットを浸透。
全員が同じ目標に向かうことで、組織のエネルギーが最大化する。 小規模な組織では、個々の方向性がバラバラだとすぐに組織全体に悪影響が出ます。
実践例:
・学校の理念を「単なるスローガン」ではなく、具体的な業務に落とし込む。
・全員がビジョンを共有できるよう、定期的に「ビジョン確認会」を実施。
(5) チーム学習(Team Learning)
組織の学習は、個人の学習の総和以上のものになる。 職員同士が学び合い、共に成長できる環境を作ることが重要です。
実践例:
・週に一度、職員が「最近学んだこと」を共有するミーティングを開催。
・問題が発生した際は「誰が悪いか」ではなく「どのプロセスを改善できるか」に焦点を当てる。
3. 実践の結果と学び
このような取り組みを続けることで、以下のような変化がありました。
・情報共有がスムーズになり、業務の属人化が減少
・問題が発生しても、職員が「なぜこれが起こったのか?」を考え、再発防止策を自発的に考えるようになった
・スタッフ間の対話が増え、チームとしての一体感が向上
学習する組織を作るには時間がかかりますが、一度文化として根付けば、組織が自律的に成長し続ける力を持つようになります。
4. まとめ:学習する組織は未来をつくる
学習する組織の考え方は、どんな規模の組織でも適用できます。特に、小規模な組織ほど、一人ひとりの成長が組織全体の成長に直結します。
組織が学び続ける仕組みを作ることは、一時的な問題解決ではなく、未来への投資です。
もし「なぜ同じ問題が繰り返されるのか?」と感じることがあれば、学習する組織の考え方を取り入れてみてください。組織の成長には、常に「なぜ?」を問い続ける姿勢が不可欠なのです。
小さな組織だからこそ、一人ひとりの成長が組織全体を動かします。
「現場でこの考え方をどう活かせるか話してみたい」「自社に合った仕組みを考えたい」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。