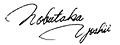第325回
解像度を上げる——AI時代に必要な視点
ここ数年、「解像度」という言葉を耳にする機会が増えた。生成AIやリッチコンテンツの普及により、誰もが一定の知識にアクセスでき、理解を深められるようになった。しかし、「情報が多いこと」と「理解が深いこと」は同義ではない。
むしろ、浅い情報を得ただけで「わかったつもり」になる危うさが広がっている。
AIやウェブ情報は非常に便利である。瞬時に回答を提示し、膨大な知識を整理して見せてくれる。しかし、そこには現場の温度感や背景にある人の思考、空気感までは含まれない。

たとえば政治の動向や社会的な予測が外れるのは、データが人間の心理や現場の微妙な空気を反映しきれないためである。AIの出す答えが専門分野の実感とずれていると感じた経験を持つ人も少なくないだろう。
調査ツールの発達によって「調べる時間」が増えた一方で、「現場で確かめる時間」が減っているという現象も起きている。便利さの裏側で、思考が浅くなる危険性が高まっているのだ。
「解像度を上げる」とは、物事をどれだけ精密に、明快に理解し、表現できるかを意味する。そのためには、深さ・広さ・構造・時間軸の四つの視点が欠かせない。
まず「深さ」とは、どこまで掘り下げられているかである。データを読むだけでなく、なぜそうなったのかを現場で確かめることが求められる。
「広さ」は、異分野や他業界まで視野を広げ、共通点や差異を見出す力である。
「構造」は、因果関係や仕組みを整理し、問題の本質を見抜く力を指す。
そして「時間軸」は、3時間後、3日後、3年後の変化を見通す洞察である。
AIが苦手とするのはこの「時間の変化」への理解であり、そこにこそ人間の想像力が生かされる。
自らの理解が曖昧なときは、「6W3H」で問い直すとよい。
すなわち、Who、What、When、Where、Why、How、How many、How much、How longの視点である。
「その課題はどこで、誰に、いつ起きているのか」と具体的に言葉にできなければ、まだ理解の解像度が足りていない証拠である。
たとえば「なぜ売上が下がったのか」と問うとき、誰の売上か、いつのデータか、どのチャネルかを明確にするだけで、課題の輪郭は格段に明確になる。特に新規事業やアイデア発想では、国内外の競合・類似サービスを100件ほど調べることで“深さ”と“広さ”の両方が上がる。
データを読む力もまた、解像度に直結する。
データそのものは中立であるが、それを解釈する人間の文脈が偏っていれば、誤った結論に導かれる。
会社の戦略、国の政策、国際情勢など、背景構造を理解して初めてデータは意味を持つ。

AIは「地図」を描くことはできても、「目的地」を決めることはできない。仮説を立て、その前提を自覚している人は情報の解像度が高い人である。逆に、データの断片だけを信じる人は、いつまでも低解像度のままにとどまる。
世界の不確実性が増す今こそ、変化を恐れず、解像度を上げる努力が必要である。
解像度を上げるとは、世界の複雑さに正面から向き合い、自分の見ている世界を疑う行為でもある。苦しい時間も多いが、その葛藤こそが理解への証である。
解像度を上げるとは、世界をより鮮やかに描き直すことである。ぼやけていた風景が少しずつ焦点を結ぶとき、私たちは初めて「わかる」という喜びを手にする。