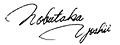第322回
「ペヤング ソースやきそば」と「アンパンマン」に共通する普遍性
「ペヤング ソースやきそば」が今年、発売から50周年を迎えました。発売当時、カップ焼きそばといえば丸い容器と粉末ソースが主流。
そんな中、「四角って食べやすい」というCMとともに、四角い容器と液体ソースで市場に登場し、大きな話題を呼びました。以来、東日本を中心に広く親しまれ、日清食品の『日清焼そばU.F.O.』や東洋水産の『マルちゃんやきそば弁当』と並ぶロングセラー商品となっています。
四角い容器の理由と差別化

ペヤングの四角いパッケージは、屋台の焼きそばに使われていた容器がヒント。丸型が主流の時代に「他社の真似はしたくない」という思いと、食べやすさの両方を追求した結果でした。
また、業界で初めて液体ソースを導入し、まろやかなウスターソースと、そのソースを吸いやすい麺で独自性を確立。味も発売以来変えていません。
名前の由来と挑戦の歴史
初代CMキャラクターは、寄席で「顔が四角い」とネタにしていた桂小益(現・9代目桂文楽)。「ペヤング」という商品名も彼が考案しました。当時、まだカップ麺は高価で「カップルで仲良く食べてほしい」という思いから、「ペアでヤングなソースやきそば」が短縮され、今の名前が生まれました。
時代が進むにつれ、さらに大胆な挑戦も。ペヤングを1つだけでは物足りない若者を見て、社長が「それなら麺を2つ入れよう」と考案した『超大盛』。さらに『GIGAMAX』、そしてYouTuberなどの反響を受け、ついには『ペタマックス』という超特大サイズまで登場しました。
時代やニーズに合わせて新しいアイデアを生み続ける姿勢が、ブランドを支え続けています。
一貫して変わらない「アンパンマン」の世界

一方、世代を超えて愛され続けるキャラクター「アンパンマン」も、普遍性を武器にしてきました。今年、NHKの朝ドラで再び注目を集めています。
アンパンマンの最大の特徴は、「ゼロ歳から四歳児が初めて出会うキャラクター」というコンセプトを50年以上変えず守り続けてきたこと。子どもたちは成長とともに卒業していきますが、次の世代の子どもたちがまた新鮮な気持ちで出会い続けます。アンパンマンは、子どもにとって自然な存在であり、まるで「空気」のような役割を果たしてきました。
普遍的なテーマ「正義」と人間味
アンパンマンの根底にあるのは、「正義とは何か?」という問いです。作者・やなせたかしさんは「お腹の減った人に食べ物を与えることが正義」という理念を掲げ、それを徹底して物語の中心に据えました。敵役のばいきんまんやドキンちゃんも、決して単なる悪役ではなく、健気さや愛嬌があり、時には優しさを見せる「人間らしさ」を持っています。
アンパンマンは単なるキャラクターを超え、やなせさん自身の人生観が反映された作品です。困っている人がいれば手を差し伸べ、頼まれたらまずやってみる――この姿勢は、今の時代にこそ必要な価値観と言えるでしょう。

ペヤングとアンパンマンの共通点
一見、全く異なる「ペヤング ソースやきそば」と「アンパンマン」ですが、両者には共通する哲学があります。
それは、「変えるべきところは大胆に変え、守るべきものは決して変えない」という姿勢です。ペヤングは、時代のニーズを敏感にキャッチし続ける一方で、味の本質は一切変えていません。アンパンマンもまた、何世代にもわたって子どもたちの心を掴むキャラクターであり続けていますが、その世界観と理念は変わらないままです。
この「普遍性と革新のバランス」が、両者を長寿ブランドとして支えてきたのです。今後も、私たちに大切な何かを示し続けてくれる存在であり続けるでしょう。
これから商品を考えたり、新たな企画を立てる際には、この両者に共通する「普遍性と革新」の考え方をぜひ参考にし、長く愛されるものづくりに取り組んでほしいと願っています。